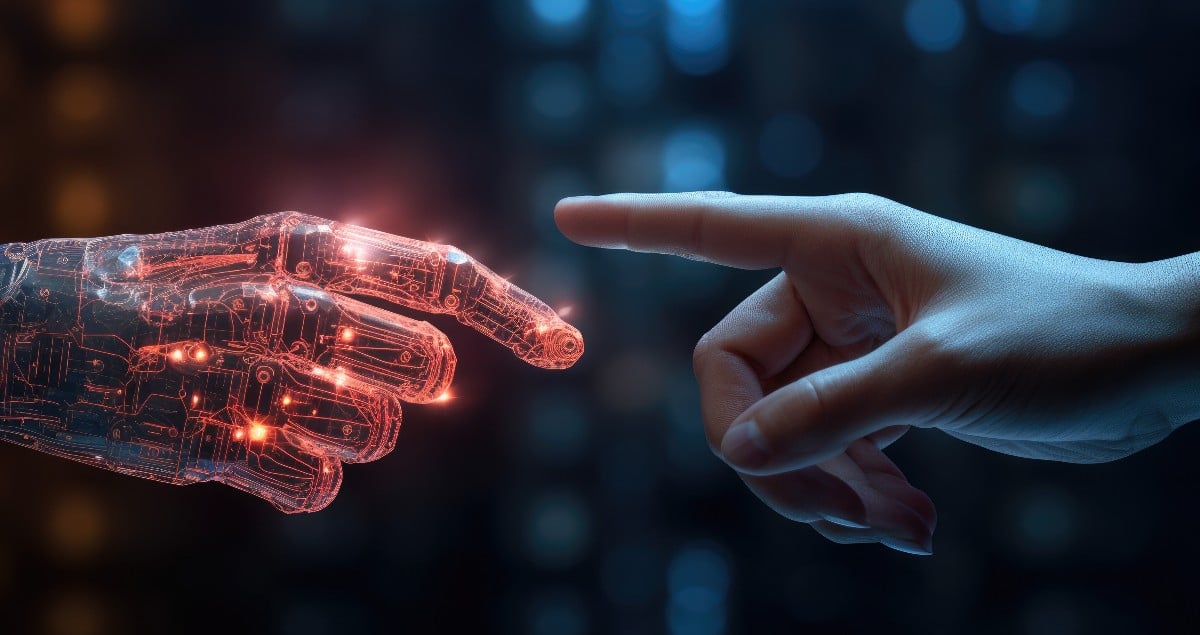Security & Exploration
Carbon Neutral World
Carbon Neutral World
Security & Exploration
Security & Exploration
Carbon Neutral World
Quality of Life